2023年10月7日。
これまでは英語に触れた時間を「YouTube」、「海外映画」、「海外ドラマ」みたいに、動画の分類で記録をしていたんだけど、今週から英語コンテンツの視聴方法に応じて2つに分類することにした。
その視聴方法とは、「多観」と「熟観」の2つだ。
これまではこの2つを「YouTube」という括りで1つにまとめて時間を記録していた。
何で分けようと思ったかというと、YouTubeを使って英語に触れるという意味では同じでも
「多観」と「熟観」で全然得られるものが違うと思ったから。
「多観」と「熟観」とは何なのか、それぞれのやり方でどういう能力が得られるのかをこれから書いていく
多観について
多観とは
多観とは、細かいことは気にせずとにかくたくさんの動画を観る視聴方法だ。
多観では、動画内で話されている単語や音のつながりなどの細かいことは気にせず大まかな内容を把握できればOKとする。
具体的な視聴スタイルは以下の通り。
手順1 見たい動画を選ぶ
手順2 字幕つけずに、巻き戻さずに視聴する
手順3 一通り見終わったら次の動画を視聴する
以上。
超シンプル。
難しいことは考えず、ひたすらたくさんの映像を視聴して英語に触れる。
ただし、多観中にやらないほうが良いと思うことが2つある。
1つ目は、字幕付きで視聴すること。
英語字幕も日本語字幕もつけずに視聴したほうがいい。
字幕をつけてしまうと、映像に100%集中できなくなる。
また、最初から字幕という答えを見てしまうと、「このシーンはどんなシーンなんだろう」とか、「ここの部分何て言ったんだ?」みたいに、自分の頭で考える力が養われなくなる。
多観の際は字幕は無しがいいと思う。
ただ、同じ映像を2回見る場合、2回目以降は字幕があってもいいと思う。
自分で考えたものを答え合わせできるから。
2つ目は、聞き流し。
映像をボーっと見るだけで英語に一切注意を向けないのでは、英語力を伸ばすという目的においてはあまり意味がない。
聴きとれなくてもいいから聴きとろうとする、耳を傾けることは重要。
一応言っておくと、聞き流しは時間の無駄というわけでもないと思う。
英語コンテンツを見たり検索したりする癖がつくから。
ただ、英語力向上という意味ではほとんど意味ないよねって話。
多観で身につく力
大まかな内容を把握すればよく、とにかくたくさんの動画を視聴することを重視するという多観の特性により、
➀話の要点を掴む力
②聴き取れなかった部分を自分の持っている知識を利用して補う力
③英語を長時間聴き続けられる力
④不完全な理解のまま視聴することに慣れる曖昧さを許容する力(tolerance of ambiguity)
この4つの力を養うことができる。
4つのうち、最後の曖昧さを許容する力については、「曖昧な理解ではいけない。映像のなかで流れてきた文は完全に理解しないといけない」と思う人もいるかもしれないけど、よく考えてみて欲しい。
言葉というものがそもそも論理的な部分と非論理的な部分を持っている。
学校で英文法を習ったかもしれないけど、全ての英文が文法規則に当てはまって構成されるわけではない。
全ての人間が、単語を発音記号のとおりに、音の変化規則のとおりに発音するわけではない。
論理的な部分で分からないことは調べたら分かるかもしれないけれど、非論理的なところでわからない部分はいくらググっても分からないことが多い。
だから、分からない状態、曖昧な理解である状態を許容しなければいずれドツボにはまる。
ドツボにはまると英語が嫌いになって挫折する可能性が高まる。
でも大丈夫。
人間には推論する力がある。
もし分からないことが出てきたとしても、「別に根拠があるわけではないけど、これってこういう意味か?」と推論する。
特に言語の習得の中で大事かつ人間固有の能力なのが、「もしかしてこういうことなんじゃね?」と閃く推論。
こういう推論を専門用語で「アブダクション推論」というらしい。
日本語学びたての赤ちゃんが、日本語の面白い間違いをするのもアブダクション推論が元になっているみたい。
アブダクション推論についてはYouTubeチャンネルの「ゆる言語学ラジオ」で取り上げられていたのが最高に面白かったので貼っておく↓
YouTubeや海外ドラマなど、映像コンテンツで英語に触れていくと、自分の知らない言葉や発音に必ず出会う。
そういうものをアブダクション推論で仮説立てて検証を繰り返すトレーニングに、多観はちょうどいい。
多観のメリット
多観のメリットはとにかく楽しいこと。
「熟観」は、楽しさだけでなく効果にも重きを置いた視聴スタイルで、頭を使うことも多いので、トレーニング負荷は少し高い。
その分、楽しい度合いは多観よりも小さいかもしれない。
楽しいと何が良いかと言うと、英語を継続しやすくなる。
ごちゃごちゃ考えずに、見たい動画を好きなだけ見ればいいスタイルでやればいいから続けやすい。
頭を使う英語の勉強の休憩として多観をするのもいいかもしれない。
また、多観によって英語の動画を大量に見ていけば、自分の大好きなYouTubeチャンネルやドラマや映画に出会える可能性を高めることができる。
それにより、次の項目で説明する「熟観」に使用できる動画もどんどん増える。
熟観について
熟観とは
熟観とは、動画内で話されている1文1文の意味や、音声変化などにも注意を向けて、細かいところまで調べたり分析したりしながら視聴する方法だ。
個人的にいいやり方だと思う熟観の視聴スタイルは、スタイルAとスタイルBの2つある。
まずはスタイルAから説明する。
スタイルAの視聴方法
手順1 まずは多観のスタイルで視聴する。
手順2 日本語字幕で何回か1通り見る。
手順3 英語で何と言っているのか1文ごとにリピートしながら聴きとる。
手順4 手順3でどうしても聴き取れなかったら速度を落とす(0.75倍、0.5倍にするなど)
手順5 手順4を何回かやってみて、それでも聴きとれなかったら英語字幕を確認する
手順6 スピーカーのモノマネをしながらシャドーイングをしてきちんと聴きとれているか確認。(余裕があれば)
以上。
英語の聴き取り能力を向上させたい場合はスタイルAの視聴方法がいいだろう。
手順2では日本語字幕を使用する。
「英語の勉強だから日本語字幕は使いたくない」と昔の自分は思っていた。
でも、言語心理学や人間の学びについて研究している大学教授の今井むつみ先生の著書、
「英語独習法」の中に面白いことが述べられていて考えが変わった。
日本語字幕を使うメリットの話だ。
日本語字幕を使用することで、「そのシーンがどういう状況なのか」という、映像の意味を考える情報処理に脳のエネルギーを消費しなくて済む。
そこで節約できたエネルギーを、「そのシーンでその人は何と言っているか」という英語の聴きとりに脳のエネルギーをフル活用することができる。
日本語字幕を付けない状態でリスニングのトレーニングをすると、状況理解と聴きとりの両方にエネルギーを割くことになり、大変だ。
日本語字幕を使うことでその負担を軽減できるというわけだ。
「いや、自分は状況を理解する力と英語の聴きとり能力両方を鍛えたいんだ!」という人は、手順2を飛ばして日本語字幕を使わずに熟観するといいだろう。
ただ、状況を理解する力、推測する力は多観でも鍛えられるという点、認知負荷が低くなり、無理をせずに続けやすくなるという点から「手順2を飛ばさずに日本語字幕を使った方がいい」というのが自分の考えだ。
(2024年7月17日追記:ただ、自分は今は日本語字幕を使わないで観るようにしている。
理由は主に2つ。
①既に900日も英語を継続できているから多少認知負荷を上げても継続し続けられるはずだと思っていること、
②日本語字幕を見てしまうと、どうしても日本語で考える癖が抜けないこと
この2つ。
特に②は大きい。日本語に頼ると日本語での理解にとどまり、日本語と学習言語の間にある微妙なニュアンスの違いを感じる能力や学習言語をその言語のまま理解する能力が付きづらくなると思った。
でもこれも状況によって柔軟に判断する必要はある。上記で書いたように、英語の聴きとりに集中して取り組みたいなら、日本語字幕をアシストとして使用するのは大いにありだと思う。)
手順6のシャドーイングはもちろんやった方がいいとは思うけど、手順5までで疲れているかもしれないから、余裕があった時や、めちゃくちゃ好きな動画のときだけやればいいと思う。
モノマネをするのは、その方が気持ちが乗って英語が理解が深まるのと、話し手の英語の発音をコピーするために注意深く耳を傾ける必要が出てくることで、耳がさらに良くなるという2つの理由がある。
ただ、英語の勉強はあくまで楽しむことが最優先だ。
苦しいと思ったら無理せず、休んだり、多観で純粋に英語コンテンツを楽しむ時間にあてた方がいい。
次にスタイルBを説明する。
スタイルBの視聴方法
手順1 まずは多観の見方で動画を見る
手順2 英語字幕を付けて文字と音声を同時に追う。ついていけなかったら1文1文リピートする。このとき、「そのシーンがどんな状況なのか」や「その人が何を伝えようとしているのか」を感じ取り、考える。
手順3 手順2を何回かやってみて、どうしても状況の理解や登場人物のセリフの意味が分からなければ日本語字幕を見る。(2024年7月17日の追記同様、今は基本的に日本語字幕を使わないようにしている。日本語訳がそのシーンの本来の意味とずれている恐れがあることと、
「日本語を使うことで翻訳癖が抜けないんじゃないか?」と思ったこと、脳が「どうせ日本語でその場状況把握できるんだから学習言語理解しなくても大丈夫かー」っていうモードになってしまって学習言語の吸収効率が下がる可能性もありそうだと思ったから。
学習言語でその状況を理解するのが難しいからこそ、あれこれ頭を働かせて学習言語とそのシーンの状況を理解しようとする。それが良いトレーニングになる。)
手順4 モノマネしながらシャドーイング
以上。
スタイルAでは英語字幕より先に日本語字幕を見ていたが、スタイルBでは英語字幕を先に見る。
英語字幕を見ることで、声だけでは把握するのが難しかったシーンを理解する補助をする。
また、英語字幕を使うことで英語の聴きとりに脳のエネルギーを使う必要がなくなり、状況を理解することに脳のエネルギーを集中させることが期待できる。
手順4でモノマネしながらシャドーイングをすることで、そのシーンの状況や登場人物の心情をより深く理解できる。
スタイルAでは聴きとり能力の向上が主たる目的、スタイルBでは状況把握能力の向上が主たる目的になっている。
熟観で身に付く力
時間をかけてじっくり取り組む熟観の特性により、
語彙力向上
英語の聴き取り能力
リーディング力向上
発音力向上
などの効果が期待できると考えている。
多観でもこれらの効果を得られるかもしれないけど。圧倒的に熟観の方が効果は大きいと思う。
熟観のメリット
成長が分かりやすい。
何回も同じ動画を見るから、聴き取れるようになった!という実感を短期で得やすい。
また、熟観した後は「今日すごくトレーニングできたなー。気持ちいい!」という感覚になる。
筋トレした後に充実感で満たされる感覚に近い。
まとめ 多観と熟観どっちも大事
パッと見た感じだと、熟観の方が英語力付きそうだな―と思うかもしれないけど、多観もかなり大事だ。
真面目な人ほど熟観ばかりしてしまうと思うんだけど、あいまいさの許容性など、多感でしか得られないメリットもある。
実際に英語でコミュニケーションをとる場面では字幕なんてないし、リピート機能もない。
だから、答え合わせできずにモヤモヤした気持ちになるかもしれない。
多観により、そのモヤモヤした気持ちへの耐性をつける。
第2言語の習得と数学の勉強は違う。
数学ではあいまいな理解のままだと取り残されてしまうけれど、言語はあいまいな理解のままでもいつの間にか理解できてしまう側面がある。
日本語を覚えていく過程を思い出せば、あいまいな理解のままでもいつの間にかちゃんと使えるようになった経験に心当たりがあるだろう。
これから先いろいろな人の意見を聴いたり本を読んだりする中で多観や熟観の視聴スタイルは変わっていくかもしれない。
そうなったら、またブログに書いてその時の自分の考えを記録しておこうと思う。
今週の英語
626〜632日目 今週の英語
◻YouTube 計4.9h
◻多観 計2.3h
◻熟観 計0.4h
◻ながら聴き 6.4h
週の途中からYouTubeを多感と熟観に分類したから、変な記録になってしまった。
Youtubeの記録の中には多観と熟観がごっちゃになっているんだけど、ほとんどは多観だと思う。
今週面白かった新しいYouTubeコンテンツは、guraのマイクラ配信の続きかな。↓
配信系は1つ1つの時間が長いので、熟観というより多観で主に使用している。
要は、guraの配信をみるときは、難しいことは考えていない。
面白いから見ている。
熟観ではMind FieldのS3EP1を視聴した↓。
Michael Stavensほど発音を真似したくなる人間はそうそういない。
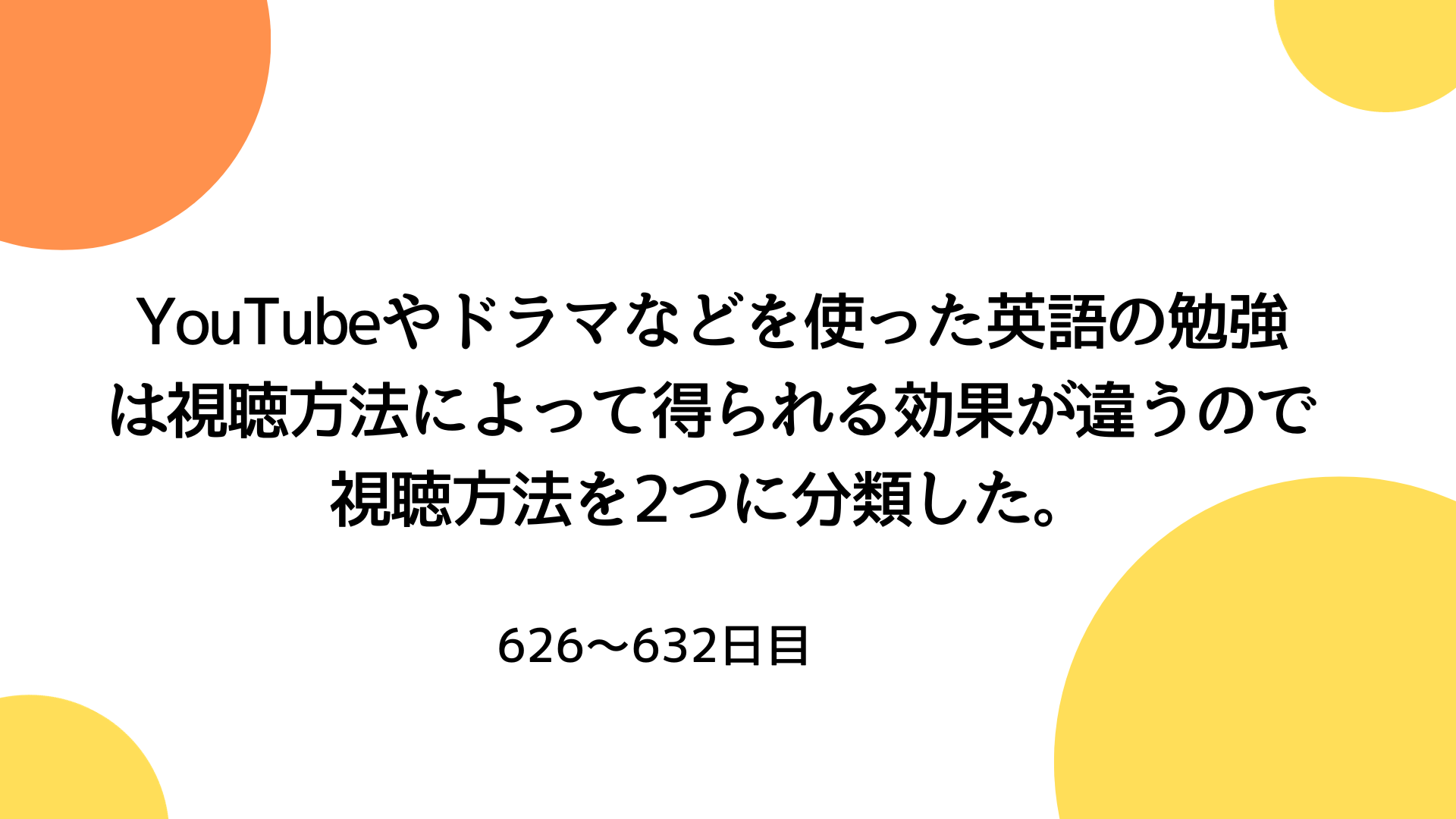


コメント